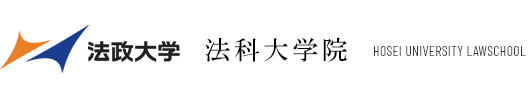カリキュラム一覧・成績評価・開講科目について
カリキュラムについて
理論と実務が融合したカリキュラム
法政大学法科大学院の教育課程は、将来法曹となったときに必要となる法的知識の基幹部分から構成される「法律基本科目群」、さらに法曹実務に不可欠な技術的知識を修得する「実務基礎科目群」、法革新の英知の蓄えに働く法比較・思想・社会科学の修得を目標とする「基礎法学・隣接科目群」、現代の法曹が課題として抱えている最先端の法領域について学ぶ「展開・先端科目群」をもって組み立てられています。このようにカリキュラムは理論と実務の有機的な関連に向けた一貫した方針で組み立てられています。
設立から今日までの経験で、基礎教育の徹底を通じた応用力の涵養という課題もますます明確になってきたことから、法律基本科目群の内容を精査し直し、限られた時間の中で最大限の効果を期待できるカリキュラムを導入しています。これにより、実定法学の基礎を系統立てて学習できる体制を強化し、並行して、展開・先端科目など他の科目群の一層の充実を図っています。
カリキュラム・マップ、カリキュラム・ツリーも合わせてご確認ください。
開講科目・進級基準・成績評価の詳細につきましては、「在学生の方へ」ページより講義ガイド・履修ガイドPDFをご覧ください。
成績評価の基準及び実施状況
成績評価を S、A+、A、A-、B+、B、B-、C+、C、C-、Dの11段階評価とし、かつ合格点を60 点以上とします。
| 合格(単位修得) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | S | A+ | A | A- | B+ | B |
| 点数 | 100-90点 | 89-87点 | 86-83点 | 82-80点 | 79-77点 | 76-73点 |
| GP | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 |
| 合格(単位修得) | 不合格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | B- | C+ | C | C- | D | E |
| 点数 | 72-70点 | 69-67点 | 66-63点 | 62-60点 | 59-0点 | 未受験・他 |
| GP | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
なお評価は単位修得の可否に関しては絶対評価とし、単位の修得を認められた者(S~ C- )のうち、 おおむねSの者が1割、A+・A・A- 評価の者が2割、B+・B・B- 評価の者が5割、C ・C・C 評価の者が2割 となることを目安とし 評価をおこなう。
これに加えて、履修登録者が少ない(概ね5名未満)科目の成績評価については、この評価割合によらず、2023年度秋学期より履修者の当該科目の成績評価は同一とならないように付与します。
また、採点評価をする最低条件として、2単位授業は14回中10回以上の出席が必要とし、5回以上の欠席で成績 評価対象外( E 評価) となる。 1単位授業は7回中5回以上の出席が必要とし、3回以上の欠席で成績 評価対象外( E 評価)となる。
修了単位数
- 法学未修者:102単位
【 修了要件単位数の内訳 】 - 2023年度以降入学者(a)34、(b)32、(c)12、(d)6、(e)14、(c)および(e)から4
- 2022年度入学者(a)34、(b)32、(c)12、(d)4、(e)16、(c)および(e)から4
- 法学既修者:76単位
【 修了要件単位数の内訳 】 - 2023年度以降入学者(a)8(1年次配当科目26単位免除)、(b)32、(c)12、(d)6、(e)14、(c)および(e)から4
- 2022年度入学者(a)8(1年次配当科目26単位免除)、(b)32、(c)12、(d)4、(e)16、(c)および(e)から4
進級要件
- 1年次から2年次
1年次配当必修科目から24単位以上修得かつ1年次配当必修科目のGPAが規定値以上であること等 - 2年次から3年次
当該年度履修の必修科目のGPAが規定値以上であること
- 詳細は「在学生の方へ」ページより講義ガイド・履修ガイドPDFをご覧ください。
- 在学生の方へ
開講科目一覧
(a)法律基本科目群 基礎科目(必修科目)
| 1年次(※既修入学者は免除) | 2年次 | 3年次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公法系 | 必修 | 憲法Ⅰ(2) 憲法Ⅱ(2) |
行政法Ⅰ(2) 行政法Ⅱ(2) |
|
| 民事系 | 必修 | 民法Ⅰ(2) 民法Ⅲ(2) 民法Ⅱ(2) 民法Ⅳ(2) 民法Ⅴ(2) 民事訴訟法Ⅰ(2) 民事訴訟法Ⅱ(2) |
商法Ⅰ(2) 商法Ⅱ(2) |
|
| 刑事系 | 必修 |
刑法Ⅰ(2) |
||
(b)法律基本科目群 応用科目
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公法系 | 必修 | 憲法演習Ⅰ(2) 憲法演習Ⅱ(2) |
行政法演習Ⅰ(2) 行政法演習Ⅱ(2) |
|
| 選択 | 憲法基礎演習(2) | 公法演習(2) | ||
| 憲法判例演習Ⅰ(2) 憲法判例演習Ⅱ(2) |
||||
| 民事系 | 必修 | 民法演習Ⅰ(2) 民法演習Ⅱ(2) 民事訴訟法演習Ⅰ(2) 民事訴訟法演習Ⅱ(2) |
商法演習Ⅰ(2) 民事法演習(2) 商法演習Ⅱ(2) |
|
| 選択 |
基礎ゼミⅠ(1)※2023年度以前入学者対象科目 基礎ゼミA(2)※2024年度以降入学者対象科目 基礎ゼミB(2)※2024年度以降入学者対象科目 |
|||
| 民事基礎演習(2) | 民法判例演習Ⅰ(1) 民法演習Ⅲ(2) 民法判例演習Ⅱ(1) |
|||
| 民事訴訟法判例演習Ⅰ(2) 民事訴訟法判例演習Ⅱ(2) |
||||
| 刑事系 | 必修 | 刑法演習Ⅰ(2) 刑事訴訟法演習Ⅰ(2) 刑法演習Ⅱ(2) 刑事訴訟法演習Ⅱ(2) |
||
| 選択 | 刑事基礎演習Ⅰ(2) 刑事訴訟法基礎演習(2)※2022年度以前入学生は刑事訴訟法Ⅱ(2)として履修 刑事基礎演習Ⅱ(2) |
刑法判例演習Ⅰ(2) 刑事訴訟法判例演習Ⅰ(2) 刑法判例演習Ⅱ(2) 刑事訴訟法判例演習Ⅱ(2) 刑事法演習(2) |
||
(c)実務基礎科目群
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 専門的 技能教育 |
必修 | 法情報調査(1) |
民事訴訟実務の基礎(2) |
||
| 選択必修 | 現代法曹論(1) | ||||
| 企業法務入門(1) ローヤリング(面接交渉)(2) クリニック1(2) クリニック2(2) クリニック3(2) クリニック4(2) |
|||||
| エクスターンシップ(2) | |||||
| 英文契約文書作成(2) | |||||
| 選択 | 刑事事実認定の基礎(2) 要件事実演習(2) |
||||
(d)基礎法学・隣接科目群
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基礎法学 | 選択 | ドイツ法(2) 法と経済学(2) 立法学(2) 法哲学(2) 法制史(2) 英米法(2) |
||
| 隣接 | 選択 | アメリカ政治論(2) 政治理論(2) 行政学(2) |
||
(e)展開・先端科目群
司法試験選択科目についてはコチラもご確認ください。
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 展開 | 選択 | 現代的契約関係法(2) 債権回収法(2) 労働法Ⅰ(2) 刑事政策(2) 経済法Ⅰ(2) 現代家族の法と手続(2) 労働法Ⅱ(2) 経済法Ⅱ(2) 民事執行・保全法(2) |
||
| 経済法演習(2) 労働法演習(2) |
||||
| 先端 | 選択 | 地方自治法(2) 知的財産法Ⅰ(2) 消費者法(2) 環境法Ⅰ(2) 企業結合法Ⅰ(2) 金融商品取引法Ⅰ(2) 倒産法Ⅰ(2) 医事法(2) 信託法(2) 企業取引法Ⅰ(2) 経済刑法(2) 国際関係法(公法系分野)Ⅰ(2) 国際関係法(私法系分野)Ⅰ(2) 国際取引法(2) 税法(2) 知的財産法Ⅱ(2) 環境法Ⅱ(2) 企業結合法Ⅱ(2) 現代人権論(2) 社会保障法(2) 金融商品取引法Ⅱ(2) 倒産法Ⅱ(2) 金融取引法(2) 企業取引法Ⅱ(2) 国際刑事法(2) 国際関係法(公法系分野Ⅱ)(2) 国際関係法(私法系分野Ⅱ)(2) 法と心理学(2) |
||
| 倒産法演習(2) | ||||
- ( )内は単位数
- 当該年度休講となる科目も記載
- 入学年度により履修できる学年が異なる科目がある